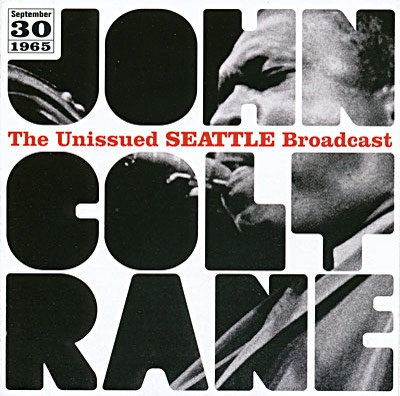Tapestry in Sound (Jimmy Garrison)
(6分4秒)
【この曲、この演奏】
ライブだけでなくスタジオ録音でもギャリソンのベース独奏が大きく取り上げられるようになっていたので、このシアトルでのライブでもギャリソンのベース独奏となるのは当然の流れなのでしょう。
コルトレーンを含め他のメンバーの演奏は一音もないこの演奏は、1971年発売の2枚組LPのD面の最後の収録されました。
ピッチカートでのベースの音が、曲名通りに絡み合っていく演奏に、聴き入っていきます。グラスの音と観客の咳払いしか聞こえないことから、ライブ会場の観衆も熱心に聴き入っていたことでしょう。
このギャリソンの物語があるベース独奏は、いつもならば曲の頭や曲中で披露されるものであり、このシアトルでも同様だったと思います。資料07にある演奏曲順からしたら、「Out of This World」に繋がるように演奏されたのかもしれません。レコード上ではこのベース独奏は、フェイド・アウトして終了となっています。
【エピソード、ファラオ・サンダースの加入、資料01から】
毛色は変わっているが正真正銘の”火の鳥”のような男だと一部で言われたリトル・ロック、すなわちファラオ・サンダースは、一九六五年にはニューヨークでテナー・サックス奏者としてコルトレーンのグループに加わっていた。
ファラオ・サンダースはアーカンザスのリトル・ロックで生まれ、フェレルと名付けられた。しかし人々は生まれ故郷の名前にちなんだニック・ネームで彼をリトル・ロックと呼んだ。その後いつの頃からかフェレルは、ファラオと呼ばれるようになった。
スプリビーがファラオ・サンダースに会ったのは、彼がマクドーガル街の「プレイハウス・カフェ」で仕事をしていて、泊まるところがないのでそこのステージの下で寝ていたときのことだ。ファラオは背が低く小柄で、音楽以外の音はどんな音も大嫌いだった。彼はまったく無口で、何か言いたいときは眼で知らせるとか、テナー・サキソフォンを鳴らすしかないような人間だった。彼はいつも倍音をふんだんに使って、キーキーと悲鳴に近い音を出したり、音階の中でも最高の音を爆発させるようにして、演奏を行っていたのだ。そこで仲間のミュージシャンたちは、彼のことを”やりすぎ”と呼んでいた。スプリビーはファラオの才能を見抜いて、彼をコルトレーンに紹介してやった。コルトレーンはいつでも若いミュージシャンの演奏を聴くのが好きだったからである。コルトレーンはサンダースを演奏に参加させたが、演奏が終わったとき、その若いサキソフォン奏者に向かって「きみはなかなか根性があるし、大変勉強熱心だ」と褒めあげた。ちょうどエリック・ドルフィーが死んで、強力なサキソフォン奏者が欲しいと思っていたので、コルトレーンはサンダースを自分のバンドに加えることにした。
【ついでにフォト】

2007年 アムステルダム
(2021年8月23日掲載)